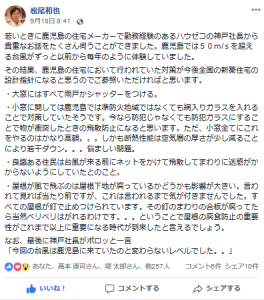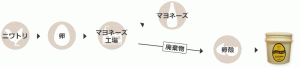雨戸やシャッターで住まいを守る
Facebookで見つけた台風対策の参考投稿をシェアしました。その内容を忘備録としてブログにまとめています。SNSのおかげで貴重な情報を簡単に共有できるのは本当にありがたいですね。
その投稿を忘備録としてblogにまとめてみます。SNSのお陰でこのような貴重な情報がシェアできるようになり、ほんとうにに有難いです!
シェア元はこちら。https://goo.gl/aqdWnb
鹿児島に学ぶ台風対策
投稿主は松尾設計室の松尾代表です。建物の通気部材専門のメーカー、ハウゼコの神戸社長と松尾設計室の松尾代表が座談会を行った時の内容を松尾代表がまとめてFBに投稿されていました。
ハウゼコの神戸社長は鹿児島に勤務経験があり、鹿児島では風速50メートルの台風は毎年経験済みで、その時の経験を話されていたようです。
鹿児島の住宅において行われていた台風対策として以下のようになります。
- 大窓にはすべて雨戸かシャッターをつける
- 小窓に関しては鹿児島では準防火地域ではなくても網入りガラスを入れる
- 飛散防止対策としてカーポートにネットをかける。
台風に慣れてくる?と他人に迷惑をかけないように対策をすることができる。
ネットはゴルフ場で使っているようなグリーンのネットが多かった。 - 屋根が飛ぶのは屋根下地が腐っているから。屋根の腐食対策が必要になってくる。
台風21号の風速50メートルを超える暴風雨で被害を受けた関西地方ですが、今後はそのような災害が全国に広がっていく可能性もあります。
今後の家づくりでも、鹿児島の住宅で行われていた対策が重要になってくると思います。
雨戸やシャッターのない住宅の現状
千葉の建売住宅でも、2階に雨戸やシャッターが無い住宅を見かけます。比較的新しい物件のほうがその傾向があるようです。
建物の印象では雨戸やシャッターが無い方がシンプルでスッキリとした印象がしますし、予算が厳しい時には減額の対象にもなってきます。
今まで大きな被害を受けたことが無い地域ですから仕方がないとも言えます。
ですが、これからの異常気象を考えると、雨戸やシャッター無しでは建物に大きな被害を及ぼす可能性が大きくなってきますから、今後の家づくりでは雨戸やシャッターは必須です。
高性能サッシと雨戸の組み合わせは可能か?
標準仕様ではない場合も設置できます!
さんむの家ではYKKの樹脂サッシを採用したのですが、カタログでは雨戸は標準仕様にはなっていませんでした。
ですが、工務店さん、YKKさんと相談し汎用の雨戸を流用して取り付け、工務店さんに鏡板を木製で作ってもらい雨戸を取りつけることができました。
納まりも苦労しましたし、コストアップになってしまったので竣工時は悩みましたが、今年の台風の被害を目にすると、費用と手間はかかりましたが、今となっては安心材料です。
家づくりでは基本性能を重視
家づくりでは住まい手の沢山の理想と実現するための予算の関係があります。
機能満載のキッチン等の設備類に目が行きがちで、断熱材や耐震性など目に見えない部分には後回しになっていませんか?
ですが完成後に追加ですることができない家の基本性能に予算をかけるべきです。
今後は雨戸やシャッターも基本性能の一つになると思いますので、雨戸やシャッターも基本性能の一部と考え、家づくりに取り入れましょう。
まとめ
台風対策は、家づくりやリフォームの際に忘れてはならない要素です。鹿児島の知見を参考に、雨戸やシャッターを採用し、住まいを守りましょう。Facebookでも引き続き情報を発信していきます!
最後に私のFBはこちらです!https://www.facebook.com/oga.kouki
カーポートのネットで飛散防止を
神戸社長のアドバイス:
カーポートのポリカは台風時にブーメランのように飛び、凶器になることがあります。ゴルフ用ネットをかけて飛散を防ぎましょう。飛散物は災害の被害を拡大させるため、各自の注意が必要です。
台風時の飛散画像をみると紙のように屋根材が飛んでいきますが、それぞれにそれなりの重量があり凶器ですよね。
>ネットをかける、ちょっとしたことで、災害は防ぐことができます。
飛散物も元をたどれば持ち主がいるわけですから、各自の注意が重要ですね。
本当に災害対策が必要な時代が到来したように思います。
追記
20190203
エコハウス大賞シンポジウム 松尾和也先生の講演より
シャッターとサッシの間に段ボールを詰めるとシャッターがバタつかないようです。