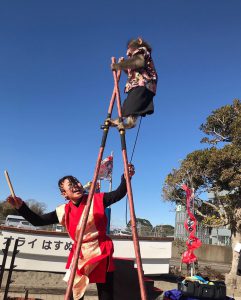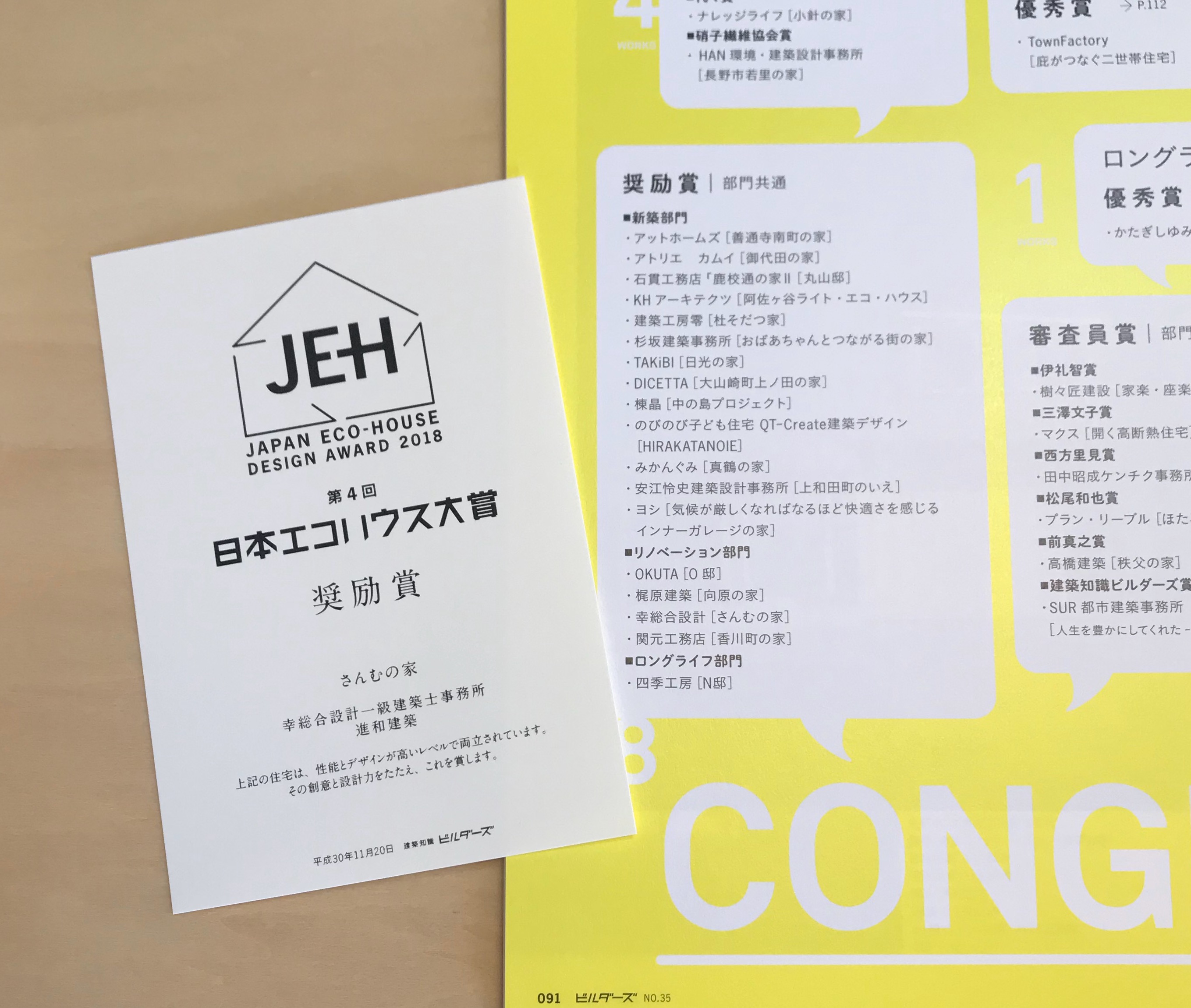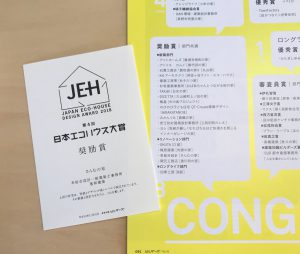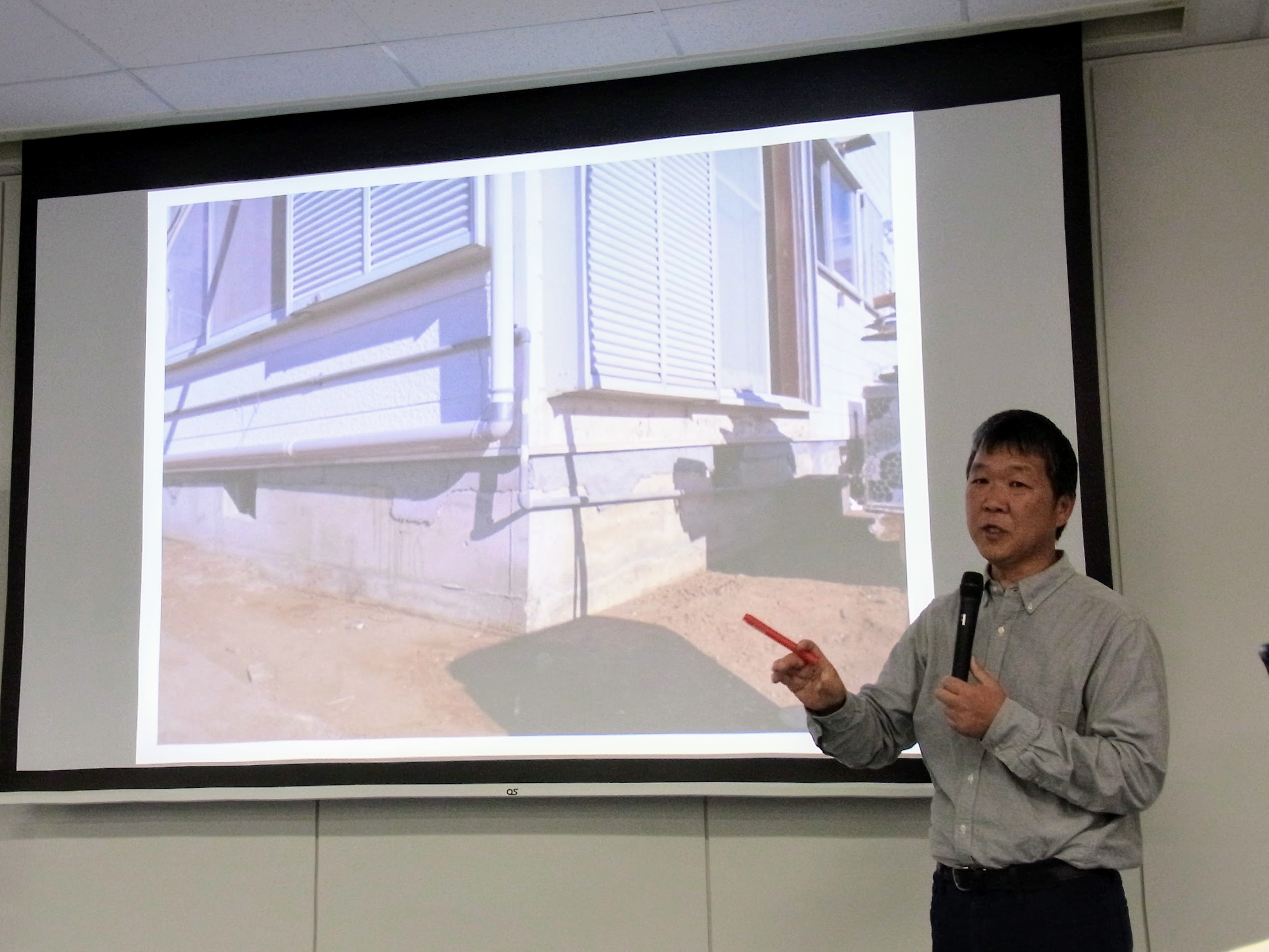今年の猛暑の中、エアコンが大活躍だったと思います。
今年の猛暑の中、エアコンが大活躍だったと思います。
寝るときの冷房を我慢していた人も今年の熱帯夜には敵わず。。。エアコンを使ったという話も聞きました。暑くなってからエアコンの故障に気が付き!猛暑のためエアコンの取り付け待ちで1ヵ月以上待ちなんて笑えない話も。
これから冬に向かっていくと今度は暖房としてエアコンを使う機会が増えてきます。
寒くなってから慌てないように今のうちからエアコンの点検をしてみるのも良いのではないでしょうか?私も仕事の合間に天気の良い日にエアコンのフィルターを外し、水洗いしました。
エアコンって1台で冷房と暖房をかねることができる素晴らしい機械なんです。ですがエアコンを嫌いな人が多いんですよね。それには理由もあるのですがそれはまたの機会に。
暖房器具は種類が沢山
 暖房は冷房と違いファンヒーター、灯油ストーブなど器具の種類が豊富です。
暖房は冷房と違いファンヒーター、灯油ストーブなど器具の種類が豊富です。
ですが灯油ストーブ等は水蒸気を発生させ、その水蒸気が冬の悩みとなる結露の原因にもなっています。
室内の空気環境も悪くなるので定期的な換気も必要になります。
そうそう、小さなお子さんがいると火傷の心配もありますね。。。
アラジンのブルーフレーム等、情緒的にはとても好ましいのですが機能面ではエアコンにかないません。
私もパーフェクションストーブの大ファンですが、メインはエアコン、パーフェクションは非常用のストーブとして待機しています。断捨離したらの声も聞こえてきますが、まあ、それは。。。。
エアコンのを選ぶときの目安って?
 ※パナソニックさんのカタログより引用
※パナソニックさんのカタログより引用
さて、今回はエアコンを購入する際の目安のお話です。
エアコンを購入するにあたって選定の目安となるのが帖数めやす(設置部屋の広さ)です。
カタログに載っているこのような表です。
この基準がつくられたのは何年まえ?
この帖数めやすですが基となっている基準はいつ頃に制定されたと思いますか?
なんと50年以上前に制定されて以降は改正されていないのです。
50年以上前の建物というと建物に断熱材は入っていません。そうなんです。めちゃくちゃ寒い無断熱の家が基になっているのです。
カタログの帖数めやすでエアコンを選ぶと、断熱されていない建物の部屋の大きさだけで選定すると言うことになるのです。
なので現在建てられている住宅の断熱材がしっかりと入った住まい対して、帖数めやすでエアコンを選ぶと必要よりも大きな能力のエアコンを選ぶことになってしまうのです。
断熱材の仕様、日射ことを考慮して選定するとほとんどんの場合、帖数めやすのエアコン選びよりも小さな能力のエアコンを選定することができます。
エアコンの能力は小さくなれば、おのずとランクが下がるので購入時の費用も少なくなります。また適切な大きさのエアコンを選ぶことは、エアコンのエネルギー効率を考えると効率の良い運転が多くなり、省エネにもつながってくるのです。
このことは、住まいの性能、暑さ寒さに対する体感によって一口に言いきれないのですが、帖数めやすのエアコン選びの真実の一つです。
エアコンを選ぶときはカタログの帖数めやすだけではなく、このようなエアコン選びができる専門家、工務店、建築士に相談すると良いと思います。
そういったところならば温熱環境のシミュレーションソフトもありますし、簡易的な計算でも十分に参考になると思います。
きっと、エアコンの選定だけでなくエアコンと建物の関係、断熱や気密との関係も知ることができると思います。
今日の一冊。エアコン以外にもとても参考になる本です。住まい手さんが読んでいたら不勉強な実務者は敵わないと思います。私もまだまだ勉強中です。
[amazon_link asins=’4822238385′ template=’ProductGrid’ store=’sachisogo-22′ marketplace=’JP’ link_id=’fb34f55d-db3d-11e8-be86-fbba982ab856′]

 豊かな色彩、楽しくデフォルメされた形を見て ”そういえばこの部分こんな形してたな”。
豊かな色彩、楽しくデフォルメされた形を見て ”そういえばこの部分こんな形してたな”。 すべての作品が展覧会や水族館など実際に現地に足を運んだり、目で見たものを作品にしているそう。
すべての作品が展覧会や水族館など実際に現地に足を運んだり、目で見たものを作品にしているそう。