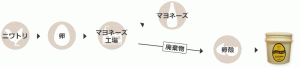天然素材は施工にコツが必要
ビーナスコートの本塗りが終わりました。
水性塗料と違い、自然系の材料は扱いにコツが必要です。シーラーの調整、材料の希釈など難しい部分があったようですが無事に施工完了しました。
本来ならば何事も無く施工できると良いのですが、必ず何か問題が発生します。ですが、原因を突き止め、対策を取ることができれば貴重な経験の一つになると考えています。
監理ポイントも見つかったので次回に施工に生かせればと考えています。
仕上がりは素晴らしく、水性塗料にはない少しざらついた肌触りで、陰影も綺麗だと思います。

さんむの家で使用したビーナスコートについて解説したいと思います
ビーナスコートは薄塗りの天然内装仕上クリーム材で、主原材料は「卵殻」と「火山灰」です。
原材料に「卵殻」を使っているのはビーナスコートだけだと思います。
メーカーさんによると「卵殻」は、マヨネーズ工場から廃棄されるものを、乾燥、粉砕の工程を経たものを原料としているそうです。
マヨネーズを作る過程で生じる卵の殻。本来でしたら処分費をかけて廃棄されるものを再利用しています。リサイクル素材であるのでエコロジーの視点から見ても満足ができる原材料です。来訪されたお客さまに、この壁、リサイクル素材で卵の殻からできてるんだよ!なんて話題にもなりそうです。
もう一つの原材料「火山灰」については皆さんご存じだと思いますが、こちらも利用価値の少ない素材です。
火山が噴火し、堆積した火山灰の処理に苦労されているニュースを見かけますよね。そんな厄介でもある素材です。
ビーナスコートはこんな二つの原材料を活用している、地球環境に負荷をかけることの少ないエコロジーな材料なのです。
機能面では、臭いや有害物質を吸着し、湿気を吸湿する効果があります。
もちろん天然素材ですから仕上りもビニールクロスには無い、天然素材の美しい質感を楽しむことができ意匠面でも満足です。
エコロジー、意匠、機能の3点を満足させることができる素材だと思います。