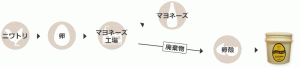計測してわかること
ビジネスの有名なフレームワークの一つにPDCAサイクルがあります。計画→実行→評価→改善→計画→と業務を改善していく手法です。
PDCAサイクルを建物の建設に当てはめてみると、設計・施工はPD、暮らし始めた状況を計測することがC、それに基づいて改善することがAになります。建物性能を改善するためにも、PDCAサイクルを回して改善していくことが大切だと考えています。
建物の使い勝手については人それぞれの感覚に寄るところが多いので計測が難しいですが、建物内の環境、室温・湿度については計測することができます。
 このような理由があり、御引渡し前の建物に室温・湿度を測定記録する装置を設置させていただきました。
このような理由があり、御引渡し前の建物に室温・湿度を測定記録する装置を設置させていただきました。
本来ならば建物の数ヶ所に設置するのが良いのですが、理由もあり(結構なお値段がしますので)1ヶ所だけ設置させていただきました。
測定データは次の設計に生かす事ができる貴重なものなので、御協力は大変有難いです。
具体的に伝えたい
今回は無断熱住宅をリフォームしたので室内の室温・湿度環境は劇的に改善しています。そのことをお伝えする時、暖かい家になりましたよ!では無く、一歩すすんで実際の状況をしっかりと把握し数値化してお伝えしたいと考えています。
室温・湿度を計測するもう一つの理由は、設計者として設計時に目指した数値目標を体感として覚えておきたいからです。
建物設計時はソフトを使用しながら数値の改善を目指すのですが、完成後、暮らし始めた家の中で、その数値がどの程度の温熱環境なのか体感することが大切だと思います。そのためにも完成後に室温・湿度を計測しています。
温熱ソフトを使った設計では数値を追い求めてしまいがちなのですが、この辺でいいでしょう みたいな丁度良い体感温度を見付けたいと思っています。
現在は本格的な冬の前なので外気温の変化はほとんどありませんが、一冬のデータを記録させていただきたいと思います。
[amazon_link asins=’4844377493′ template=’ProductGrid’ store=’sachisogo-22′ marketplace=’JP’ link_id=’3ddd58c0-c455-11e7-86a5-434d183928f7′]