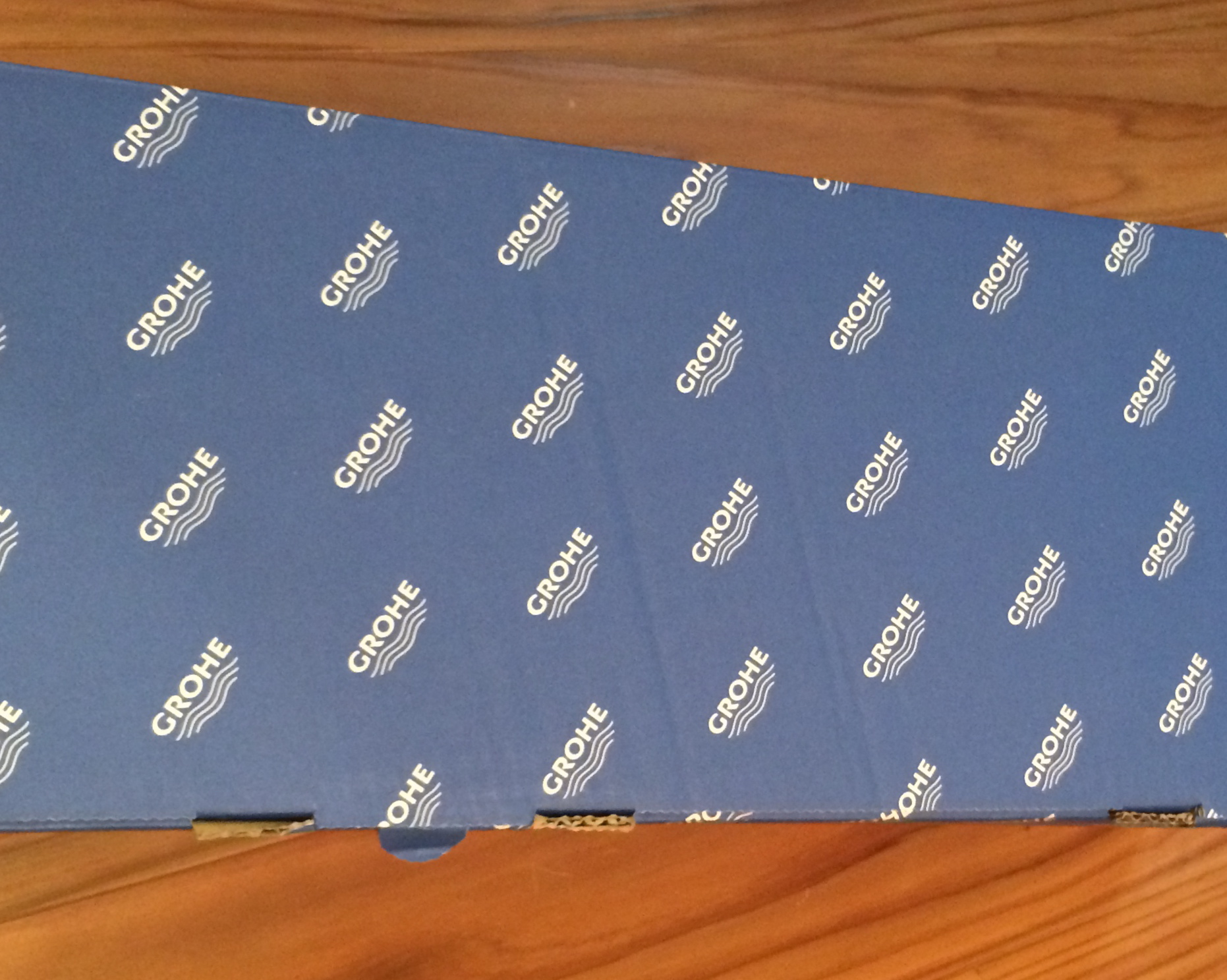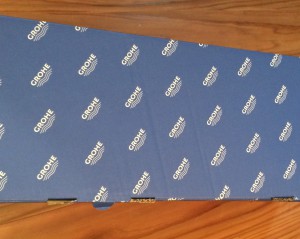洗面カウンターを造作にて制作する時、カウンター材、洗面器、水栓の選択は悩みますね。
悩ましい時間ですが、とても楽しい時間でもあります。
お客様から特に要望が無い時は、私は昔ながらの埋め込み式の洗面ボールを提案します。
木製カウンターと合わせる洗面器のお薦めはTOTO L851CUです。簡素なデザイン、洗面容量も大きく使い勝手がとても良いです。
しかし、すでに廃盤になりカタログ落ちしているのです。
現在も廃盤ながらも注文製作をしてくれていましたが陶器が破損したときのメンテナンスを考えると採用する事が難しいのが残念です。
なので、復活して欲しい建材のNO1が TOTO L851CU です。
そんなL851CU、カタログ落ちの詳しい理由は解りませんが、監理をしていると施工上の不安を少々感じます。カウンター板をくり抜いて洗面ボールを設置し、シリコンシールで固定する方法は施工する職人さんの技術に頼る部分が大きく施工不良が起きやすいのでしょう(もちろん、そのような事故が無いよう設計監理を行います)
狭い洗面カウンター台の中に頭を突っ込んでシリコンシールを打つのは大変ですし、施工不良を引き起こす可能性も大きいです。洗面ボールとカウンター板の隙間の漏水対策もシリコンシールだけに頼っているのも不安な面もあります。

このようなクレーム対策や、マーケティン等により水回りのメーカー各社が販売している洗面カウンターは、このような対策等がとられた安全側の設計がされた商品が並びます。狭い洗面スペースで最大限の大きさ容量を確保して漏水対策も完璧です。そのような流れの中、施工不良が生じやすい製品は、製品自体の魅力とは別に、残念ながらカタログ落ちしていくのでしょう。
ですが、木製カウンターにL851CUの組み合わせは完璧な商品にない魅力があります。
水栓脇のちょっとしたスペースがコップ置きとして使えたりして使い勝手も良いのです。
一見すると何の変哲も無い洗面ボールですが使ってみると”普通の良さ”があります。
TOTOさんに、是非復活をお願いしたい一品です!
完成したプロジェクトへの記事:木質パネル工法住宅のリフォーム:天然素材と経年変化を楽しむ空間へ