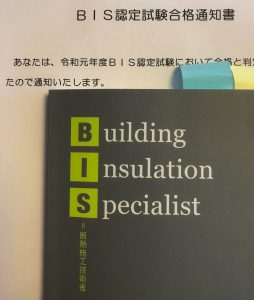先日、コロナウィルスの感染拡大を受け、パッシブハウス・ジャパンより
”換気と住宅にまつわるお話”がFacebookに投稿されました。
ご覧になっていない方に向けて再掲させていただきます。※一部、見出しを付けています
とてもわかりやすい内容ですのでご覧いただければと思います。
20200307追記
パッシブハウス・ジャパンのHPにも掲載されています。
特別寄稿 ~住宅と換気にまつわるお話~
以下貼り付け
——————–
住宅と換気にまつわるお話
非営利型一般社団法人パッシブハウス・ジャパン
森みわ・松尾和也・竹内昌義
2020年3月4日
今回のコロナウィルスの感染拡大を受け、「住宅や建築空間の換気は十分なのか?」といった不安をお持ちの方が増えているように見受けられます。これまで住宅をはじめとする建築の換気設備について、あまり意識をした事が無い方が圧倒的多数だと思いますので、ここでパッシブハウス・ジャパンより、主に住宅を例として換気のしくみについて解説させて頂きます。
なぜ換気が必要なのか?
室内に人が滞在すると臭いが籠ったり、CO2濃度や湿度が上昇し、家具や建材からはホルムアルデヒドをはじめとするVOCが発生したりすることから、健康的な住環境を確保するため、日本では建築基準法により24時間換気設備の設置が義務付けられているのは皆さんもご存知かもしれません。
具体的には、1時間に建物内の気積の半分の空気の入れ替えが必要で(これを0.5回/hと表します)、2時間に1回、建物内の全ての気積分の空気が入れ替わる計算となります。
換気のしくみ 日本の一般的住宅場合
日本の通常の住宅(一般的な既存建築、または施主が特に何もこだわらずに建てた新築)において、この要求を満たすための換気設備というのは基本、トイレや浴室の天井等に設けられた排気ファンと、それに対応する居室の壁に取り付けられた自然給気口と呼ばれる穴ぼこです。
匂いや湿気が発生するトイレや浴室から、排気ファンで空気を引っ張れば、自然と居室の穴ぼこから新鮮空気が入ってくるであろうという、希望的観測に基づくコンセプトと言えます(これを業界では三種換気と呼びます)。
この換気方式を成立させるためには、排気ファンで空気を引っ張った際、建物内が負圧状態になる事が条件になるのはお判り頂けるでしょうか?ストローに穴が空いていては、何時まで吸ってもジュースが口元まで上がってこないのと同じで、もし家じゅう隙間だらけで、高気密とは無縁な作りであったら、恐らく新鮮空気はトイレの窓の隙間等(よりによってそこにガラスルーバー窓?!)から入り込んで、トイレの臭いは取れたけれども居室の空気は入れ替わらないという現象が起きます。
日本の一般的住宅での換気の現状ー三種換気について
大半の気密性能が伴わない三種換気の住宅では、特に2階の自然給気口からは新鮮空気が入ってこないばかりか、場合によっては自然排気口になっている家もある程です。
更に冬期になると、居室の壁の穴ぼこから冷たい外気がスースーと入ってきて不快であるという事で、住まい手がこの穴ぼこを塞いでしまうケースが多発します。断熱性能の伴わない家を、一生懸命温めようとする結果、換気と暖房が両立しなくなり、住まい手は空気の質よりも、空気の暖かさを選択してしまいがちなのです。
「日本の伝統家屋はもともと隙間だらけで勝手に換気がなされ、大変理に叶っていた」という意見は、重要文化財級の伝統家屋のお話であり、現代の一般的な建築(即ち、相変わらず隙間だらけではあるものの耐震性能の向上により伝統家屋ほどスカスカでもない建築)においては、この勝手な換気は成立していないケースが大半と認識して頂くべきでしょう。
一種換気・二種換気って?
そもそも換気があまり機能していない現代の日本の家が、省エネルギー性や快適性向上の観点から近年、高気密高断熱化の傾向にあり、その過程で計画的な換気の重要性が理解され始めました。現在では熱交換技術の発達もあり、排気側だけでなく、給気側もファンで引っ張る“一種換気”というシステムも導入事例が増えています。
これらの建築では、施工後に実際の換気風量を測定し、各部屋に必要な給気量または排気量が確保されているかを確認する必要があり、ドイツのパッシブハウス認定でもこれが義務付けられています。
また、余談ですが医療施設などでは新鮮空気を給気側のファンで室内に押し込み、建物内を若干の加圧状態にする事によって、外部から埃などが入り込まないようにする“二種換気”なる方法も以前から採用されています。
三種換気のチェック方法
今皆さんがお住まいの住宅で、換気性能に関して不安がある方は、まず三種換気の場合、居室の自然給気口が塞がっていないかをチェックしてみてください。
排気ファンに繋がる吸い込み口にフィルター等が設けられている場合は、埃等で目詰まりしていないかもチェックします。
浴室やトイレ、廊下など、排気経路の窓が常に開いている、または床が隙間だらけだと、居室の自然給気口からは新鮮空気が入りませんので、注意が必要です。
それでもやはり気になる方は市販のCO2センサーを購入してみることで、人が滞在している部屋できちんと換気が出来ているかを確認することが出来ます。就寝中も寝室でCO2濃度が1000ppmを超えない状態が理想です(但し小さいお子さんと川の字で寝ている家庭ではCO2発生量が多すぎるため、1500ppmが妥当)。
一種換気のチェック方法
一種換気の住宅で、竣工時に換気風量チェックを行っていない場合は、今から測定の依頼をするのも不安解消に効果的でしょう。パッシブハウス・ジャパンでは風量調整レポートの書式を無償配布しておりますので、お問い合わせください。
今は暖房シーズンですので、これらの対策無しに、窓を常に開放する事は過剰換気(即ち過乾燥)のリスクと暖房用消費エネルギー増大の観点からあまりお勧め出来ません。
住宅の空調について
さて、換気の話は以上ですが、冷暖房期には室内を快適な温度に保つために、空調を行います(床暖房等の輻射暖房のケースはこれに当てはまりません)。
通常のルームエアコンの仕事は、室内の空気を加温もしくは冷却し、それをまた室内に放出するというもので、換気機能は一切ありません。ルームエアコンを一部屋に1台ずつ設置するような、日本の住宅で一般的なやり方では、その部屋の中の空気をぐるぐる回しているだけですが、床下エアコンやダクト式エアコンのように、1台のエアコンで住宅内の複数の部屋を暖めようとする設計では、複数の部屋の空気がぐるぐると回ります。
住宅の断熱性能が向上すると、そもそも1台のエアコンで家一軒が空調出来てしまうため、このような方式に移行していきます。
ビル空調のしくみ
また、ホテルやオフィスのような大型施設では、もともと断熱性能とは無関係に、ビル空調方式と言って複数の部屋から集めた空気を空調し、また複数の部屋に空気を再分配しています。
このやり方はダイヤモンドプリンセス号のようなクルーズ船に限った手法ではなく、非住宅建築ではごくごく一般的な手法なのです。この換気機能と空調機能は、全く異なる目的のために設計されており、目的が異なるため、換気に必要な空気の送風量と、空調に必要な空気の送風量とは、全く次元が異なります。
簡単に言うと、先ほど述べた0.5回/hの換気量に必要な空気の送風は、建物を空調する(例えば冬は室温20℃以上、夏は25℃以下等に維持する)ために必要な空気の送風量よりも圧倒的に少なく、その差は、建物の断熱気密性能の低下によってどんどん大きくなります。
その結果、もしもビル空調方式で、換気と空調という二つの機能を融合し、同じ送風ファンで供給する設計とする場合、そのシステムが扱う送風量の、恐らく3割が換気用の新鮮空気、残りの7割は空調用にぐるぐる循環する空気、という事になります。
これを言い換えると、必要換気量の3倍の量の空気を空調機に通すという意味です。この空調用にぐるぐる循環する空気の経路に、ウィルス等を除去する電気的なフィルター等を取り付けている事例もまれに見かけますが、まだまだ一般的ではありません。
パッシブハウスの空調のしくみ
一方、換気風量のみで空調するという一見無謀なテーマに20年間以上前から取り組んでいるのがドイツ発祥のパッシブハウスです。
これはもともとウィルス感染対策が目的ではなく、純粋に健康的で省エネルギーな建築を追い求めていった結果、断熱気密性能の担保に加え、風や太陽といった自然エネルギーを活用する、いわゆる“パッシブデザイン”を駆使することで、冷暖房需要を極限まで減らせることに着目し、換気装置に補助熱源が取り付けられたという経緯でした。
パッシブハウス性能にまで至らなくても、近年の国内の高性能住宅では、必要換気量の1.5~2倍の空気の送風量で全館を空調出来る状態にはなりつつあります。建物の断熱気密性能が向上すると、これまでよりも少ない循環風量で設定室温に達する事が出来るということです。
まとめ
繰り返しになりますが、気密性能の伴わない建物では、従来型の三種換気であっても必要な換気量を確保できていないこと、冷暖房期に空調用の空気が建物内を循環する割合は、建物の断熱気密性能が不足する場合程大きくなる事を皆さんにご理解頂きたいと思います。
最後に コロナウイルスへの対策として
また今回のコロナウィルス感染への対策として、換気量に意識が向きがちですが、換気回数を上げるとその分室内の水分量は減り、暖房期には室内が過乾燥に陥る傾向もあるので十分注意が必要です。感染予防には過乾燥は禁物だからです。
免疫力の低下によりウィルスに感染しやすくなっては本末転倒です。是非とも適切な換気量且つ十分暖かい家の中で過ごし、生活習慣の見直しで体温を上げる工夫も取り入れながら、皆さんの免疫力を高めて頂きますようお願いいたします。
また、宅内での飛沫や接触による感染の予防のため、手洗いとうがいの習慣もお忘れなく!!
そして体調がすぐれない時は無理をせず、休息を取りましょう。それが皆さんのご家族や周りの人に迷惑を掛けないためにも一番重要な事かも知れません・・。
非営利型一般社団法人パッシブハウス・ジャパン
森みわ・松尾和也・竹内昌義